| 1. はじめに:さわり |
弦の振動を楽器の他の部分に軽く接触させることで生じる濁った音を「さわり」と呼んだりします。日本では琵琶や三味線、インドではシタールに代表される音色です。
日本の「さわり」、インドでは「ジャワリ(jawari)」というようで、言葉も似ています。音響工学的には、さわりの構造は高音域を増しサスティンが長くなる特性をもたらすようで、単にビビって濁ってるわけではありません。
西洋音楽は、澄んだ音を追求して発展してきたようですが、東洋やアフリカには、濁ったさわり音が重要視される音楽も多く残っています。打楽器系では、アフリカのカリンバやブラジルのビリンバウなんかは、さわり音が特徴的な楽器です。
個人的には、ロック系のファズやディストーションの音も、さわりの一種では?と思ってます。ていうか「さわりはロック」です。
今回はさわりに関連して、ギターの改造=ギター用のシタール風ブリッジ作成についてまとめてみました。
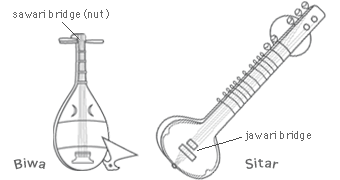
-- figure1: 琵琶とさわり/シタールとジャワリ
ちなみに、はじまりの意味で使われがちな「さわり(触り)」という言葉は、「重要な部分」という意味で使うのが正しいとのこと。語源は義太夫用語で、他の流派の節回しに触る=聴きどころ、ということらしい。
楽器の振動が他の部分に「さわる(触る、障る?)」=聴きどころ、ということかも知れない。 |
|

